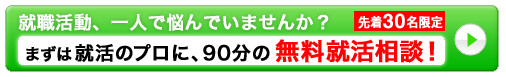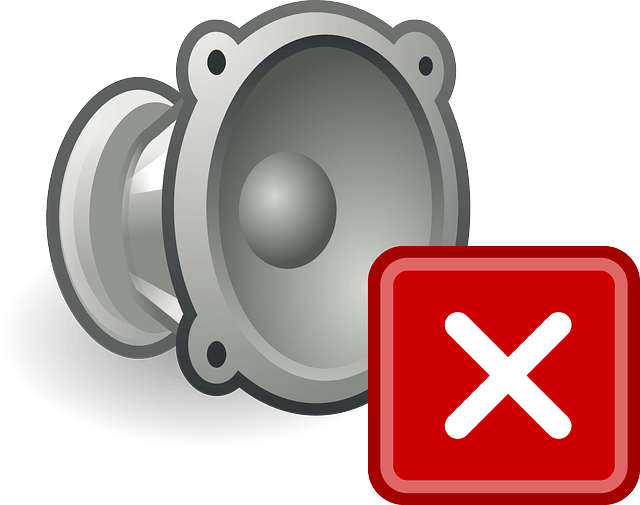
「こころの状態」が良くないとき、つまりは何か心配事があったり、不安なことがあったり、面白くないと感じている時の声は、声が震える・声が小さくなるなど、そうではない「こころの状態」が良い時に比べると覇気がなくなってしまいます。
例えば、
- 自己肯定感が薄い(自信が持てない)
- まあ、いいやと思ってしまう
- ストレスがある
- どうせ思考
- マイナス思考
- 毎日がつまらない
- 仔細なことに腹がたつ
- 人や環境のせいにする
このような精神状態にあると、決していい声、自信のある声・大きい声は出てきません。
自信のある声を出す良好な精神状態を保つために
精神状態は、以前のブログで紹介した「自己肯定感」の低さや、「他者軽視感」の高さと大きな関連があります。
上に例示した「良くない」精神状態になると面接で声が小さくなってしまったり、声が震えることの原因になります。
「自己肯定感」を高く「他者軽視感」を低めるよう、以下のような気持ちで日々を送ることをお勧めします。
- 楽しいことを考えて、ワクワク感を味わう
- 自分の将来に対して、夢や希望を持つ
- ありがとうやお陰様という感謝の心を持つ
- 目標や目的に向かう生活をする
ことです。これらが自信のある声を出す秘訣です。
自分の気持ちとの向き合い方
しかし、現実の生活の中では、頭では分かっていても、なかなかうまくは行かないこともあります。そこで、自分の気持ちとの向き合い方の良い方法を紹介します。岸英光氏の著書にある「悩みを味わえば視界が開けてくる」という1節です。
『「味わう」というのは、例えば自分の気持ちを、眺めて、さわって、動かしてみて、なめてみて、舌にのせてみて、噛んでみて、味を知り、味を確認するという感覚です。つまり、自分自身の気持ちとコミュニケーションをもつのです。自分の気持ちを味わっているうちに気持ちが落ち着き、それまで見えなかったものがはっきりしてきたりします。自分の感情を味わい、気持ちを味わい、過去を味わえば、だんだん本質が見えてきます。人は悩んでいるとき、「こうすれば、こうなってしまう。ああすれば、ああなってしまう。」とぐるぐると同じ場所を回って判断することができなくなります。放っておくと、悩みはどんどん深くなっていきます。そうした時に、自分がどんなことに悩んでいるのかを味わってみるのです。すると、ぐるぐる同じところを回っていることがよく見えてきて、バカバカしくなります。悩みに迷い込み、整理がつかない状態になっているときは、自分でその悩みを味わうことです。自分自身と切り離して、悩みだけを見つめ、さわり、味わうことで、すっと視界が開けてくるのです。』
実に、含蓄のある言葉ではないでしょうか?
勿論、こうしたこと以外にも、「スポーツ観戦で大きな声を出す」「カラオケで熱唱する」「友達とおしゃべりをする」「遊園地で絶叫マシンに乗って、大声で叫ぶ」「散歩する」「お風呂でリラックスする」等により、ストレスを発散することも有効な方法の1つですが、その効果は一時的なものに終わりがちです。
是非、精神状態が「良くない」と感じたら、先ほどの岸コーチの文章を取り出して、何度も繰り返し味わってみてください。
自信のない声をなくすために
精神状態を悪化させないためには、普段から「プラスの(前向きな)言葉を使うことも大切です。例えば、「嬉しい」「楽しい」「大好き」「幸せ」「素晴らしい」などです。
日本では古来より、「言霊」という言葉があり「言葉には魂が宿る」と信じられてきました。毎日の生活の中で、プラスの言葉を口に出すことで、気持ちは前向きになります。